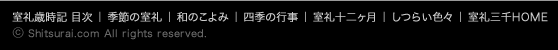芹(せり)・薺(なずな)・御形(ごぎょう)・はこべら・仏の座(ほとけのざ)・菘(すずな)・すずしろ
<春の七草
>
七草の風習
七草とは一月七日の朝に七種の菜の入った粥を食べる習わしのことをいいます。現在でも全国的に行われている七日正月の行事で、邪気を祓うとされています。また、七草には様々な薬効があるといわれています。
七草の由来
古くは子(ね)の日の遊びともいわれ、平安時代には正月最初の子の日に野に出て若菜をつむ風習がありました。「延喜式」に見られる七種粥と、若菜摘みの古俗と、中国の人日の行事が合わさり、七草粥になったのであろうといわれています。
七草粥の習わしは江戸時代まではかなりに盛んに行われていた様ですが、幕末頃の民間では七種のうち1、2種の菜を入れるだけだったとか。
今日でも 七草の種類は地域によって違いがあり、七種に限らない所もあります。
「延喜式」平安時代中頃
宮中で正月十五日に供御(くご)の粥として用いられたもの。 この頃は穀類でした。
米・粟・黍・稗子・みの・胡麻・小豆
七草囃子と七草叩き
六日の夜から七日の早朝にかけて、まな板の上に七つの道具をそろえて七草を叩き刻みます。
歳徳神の方に向かって(例えば年神棚の前などで)叩くならわしがあった様です。
七種の道具 : 火箸・擂粉木・杓子・おろし金・菜箸・火吹竹・割薪 など
このときに唱える言葉が囃子歌となって七草囃子として各地に伝えられています。詞は地域によって様々です。
>>
七草の写真と薬効(別ウィンドウ)
【正月料理の頁】
 お屠蘇 お屠蘇
 お雑煮 お雑煮
 お節料理 お節料理
 祝いの食品のいわれ 祝いの食品のいわれ
 七草 七草
 七草粥の作り方 七草粥の作り方
|