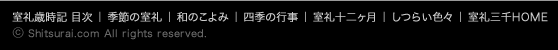お節料理はその一つ一つに一年の無病息災と幸せを願う心がこめられた縁起物です。
・三つ肴
関東:黒豆、数の子、五万米
関西:黒豆、数の子、敲き牛蒡
・黒豆
まめで健康に暮らせますように。一年の無病息災を願います。 昭和初め頃までは座禅豆と呼ばれており、座禅豆を正月にいただく風は江戸時代後期にはあった様です。当時は黒大豆を醤油味で煮た固く塩辛いものと、砂糖で甘く煮たものと二通りありました。明治に入ると、甘く煮たものを用いる様になったといわれています。
・数の子
鰊の子。その名の由来はアイヌ語の「カド」に通じ、「かどのこ」がかずの子になったとか。
数の子は、多産・子孫繁栄を意味します。
・五万米(ごまめ、田作りとも)
片口鰯の幼魚を素干しにしたもの。 炒って甘辛く煮詰めます。田作りの語源は田畑の肥料として用いたとか、豊作祈念の田植え祝いの膳に用いられたからともいわれています。田作りは小殿腹(ことのばら)ともよばれ子孫繁栄を願うところから、またごまめの「まめ」は健全の意から縁起をかついで正月の膳に用いられる様になったそうです。
・たたきごぼう
アク抜きした牛蒡をゆでて、すりこぎで叩き、醤油等で煮たりしたもの。豊年に飛んでくる瑞鳥を表しているといわれ、豊作と息災を願ったものです。
・きんとん(金団)
黄金色の丸い小判に見立てられ、財のたまる願いにかけたものです。
金団は金飩とも書き、もともとは平安時代に中国から渡ってきた唐菓子のことで、
飩は蒸した餅のことをいいました。
・伊達巻き
巻いてある様から「結び」「むつむ」を意味しています 。仲むつまじく。
・かまごこ(蒲鉾)
日の出の形に似ていることから、新しい門出を祝うものとして。もとは竹に魚のすりみをつけて焼いたものが蒲の穂に似ていることから蒲鉾と名付けられ、のちに今みられる様な板付のものとなりました。お節料理に用いられる紅白の蒲鉾は、赤は魔よけ、白は清浄を表しているといわれています。
・八つ頭
親芋が大きく、八方に頭があるように見えるため人の頭となります様にとの願いがこめられています。
・蓮根
たくさん穴があることから、将来の見通しがきくといわれています。
・慈姑(くわい)
ひとつの根から毎年芽がでるため、子孫繁栄の意味が込められています。
・柚子
柚は柑橘類です。柑橘の橘は吉に音が通じます。
また、大小不同なく育つことから、豊作を祈る気持ちを表しています。
・あわび
おめでたい贈り物に用いられる熨斗鮑は、あわびの肉を薄く切って長く伸ばしたもの。お付き合いやおめでたいことが長く続きます様にとの願いが込められています。
・昆布巻
昆布は慶ぶの意、そして巻は「結び」「むつむ」を意味しています
。
・海老
寿老の縁起物とされています。
【正月料理の頁】
 お屠蘇 お屠蘇
 お雑煮 お雑煮
 お節料理 お節料理
 祝いの食品のいわれ 祝いの食品のいわれ
 七草 七草
 七草粥の作り方 七草粥の作り方
|