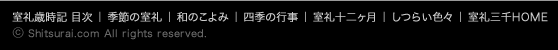|
鏡餅 その由来
鏡餅とは神供用の丸くて平たい餅のことで、お供え、お鏡とも呼ばれています。
もともと年神に供える餅のことを言いました。 昔から神仏の祭りには餅を供えるならわしが広くみられました。
鏡餅という名は、鏡の形に由来します。古く、鏡は神の依るところと考えられ、神事に使われ宗教的な意味合いの濃いものでした。今日でも、神社の祭事には薄い鏡状の丸餅を供える所があるそうです。
鏡餅の供え方
鏡餅を供える場所は、床の間や神棚、仏壇、年棚といった所から、近年では住宅事情により多様化してきています。
三方に奉書紙を垂らして敷き、ゆずり葉と裏白をのせ大小二つの鏡餅を重ね、その上に橙の他、串柿、昆布などを飾ったものが一般には知られていますが、飾り方も地域や家によって違いがあります。
そもそもこのような形になったのは室町以降と言われています。建築様式が寝殿づくりから書院づくりへ移り、床の間が設けられる様になり、床飾りとして広まったと考えられます。武家社会では武家餅(具足餅)といって、鎧兜などの具足をしつらい、その前に鏡餅を供えて家の繁栄を願うところも多くあった様です。
鏡開き
供えた餅を下げる日を鏡開きといいます。 一月十一日に行う所が多く鏡あげ、オカザリコワシとも呼ばれており、餅を叩き割って雑煮や雑炊にして食します。
正月に鏡餅を供えることは一般化されていますが、地域によっては、正月の儀礼食に餅を用いず、芋や麺類を用いている所も少なくありません。
【お供えと飾りの頁】
 鏡餅 鏡餅
 お飾り 目出度いいわれ お飾り 目出度いいわれ
 門松・注連飾り 門松・注連飾り
|