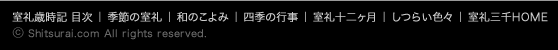お雑煮のいわれ
お雑煮は 正月の祝いの食物です。
一説に、もとは大晦日の夜に年神に供えたものを、元日の朝におろし、汁で煮、年神と人が一緒のものを食べる「直会」といわれてます。
雑煮で正月を祝うようになったのは室町時代といわれています。雑煮は、餅が臓腑を保養するところから「保臓(ほうぞう)」といい、本字は烹雑で、烹は煮と同じであるから雑煮になったそうです。(貞丈雜記)
雑煮は地域によって色々な料理法があります。だしや具ひとつとってみても、実に様々です。
餅なし正月
雑煮に餅を入れる地域は多くありますが、例えば香川県では、 餅の代用としてカンノメと呼ばれるものを入れます。
(カンノメとは粳米8割、糯米2割をひいて小判型の団子にしたもの) また元旦に餅を食べることを忌む餅なし正月の伝承も各地に残っています。
>> 各地の雑煮の一例へ(別ウィンドウ)
【正月料理の頁】
 お屠蘇 お屠蘇
 お雑煮 お雑煮
 お節料理 お節料理
 祝いの食品のいわれ 祝いの食品のいわれ
 七草 七草
 七草粥の作り方 七草粥の作り方
|