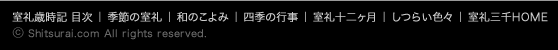凧揚げ
お正月の野外での代表的な遊びです。竹などの骨組みに紙またはビニールをはって糸をつけ、風を利用して空中に揚げる遊びで、今日でもお正月の風物詩として多くみられます。凧揚げが一般に盛んになったのは、江戸時代からです。庶民の間でその人気ぶりはすごく、明暦元年(1655)年からは幕府から通行妨害などを理由にしばしば禁止令が出されるほどでした。凧は種類も多く、
色形も多彩で、各地で作られています。凧の呼称も地域によって様々です。
独楽廻し
円い木製の胴に心棒を貫き、これを中心にし て回転させてする遊びです。 奈良時代に唐から高麗(こま;韓国北西部)を経て伝えられたのが、こま(独楽)という名前
の由来といわれています。日本へ伝えられた当初は宮中の年中行事の余興として遊ばれていましたが、平安時代になっ
て貴族の遊戯となり、平安後期に子供の遊び道具となりました。江戸時代には庶民の遊びとなり、博多独楽・八方独楽・お花独楽・
叩き独楽など、多くの独楽が作られました。
羽根つき
羽子板で羽根を突く遊びです。 羽子板は、古くは「こぎ板」と呼ばれ、幼児が蚊に刺されないまじないとして、羽根を突き合っ
たのが始まりといわれています。 羽根突きが盛んになったのは、江戸時代 の元禄の頃といわれ、町家の子女の遊びとして発達しました。昔は杉で作られていた羽子板も文化文政期には軽い材質の桐で作るようになり、絵も押し絵や役者の似顔絵などが描かれ多彩になっていきます。今日では羽子板市にも見られる様に、縁起物としての飾りや、美術品としての価値が高いようです。
歌留多取り
小倉百人一首の和歌が一首ごとに書かれた読み札と、下の句のみ書かれた取り札を使い、下の句を書いたものを競技者の間にばらまいて、一人が上の句を読み、競技者がそれに続く下の句が書いてある札を取り、多く取った者が勝ちとなります。
加留多は「歌骨碑」とも書きます。
福笑い
タオルなどで目隠しを して、大きな紙にお多福の顔の輪郭のみが描かれたところに、眉・目・鼻・口.耳の形をした紙片を載せていくという遊び。目隠しをして行うので、
目・鼻・口などがとんでもない場所に置かれ、おもしろい顔にでき上がり、そのお多福の顔をみんなで見て楽しむといった素朴な遊びです。
双六
双六は室内遊戯の中でも、最も古い遊び の一つであり、インドに起こり、中国を経
て日本へ伝わり、古くから賭けの対象となりました。日本へは、奈良時代以前に伝
わったといわれています。正倉院に残る双六盤は将棋 や碁に似た形で、二人用の遊戯具だったことがうかがえます。
現在のような双六になったのは江戸時代 のことで、出世双六と道中双六が作られたのもこの頃のことです。