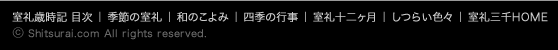|
門松
正月に家の門口に立てる松のこと。松飾り、門の松とも言います。 古くから門松は年神の依代と考えられていました。門松の形態と材料は地域によって様々で、興味深いものがあります。また餅同様、正月に松飾りを用いない所もあります。
飾り方もいく通りもありますが、年末のうちに飾り付けを済ますのが通例です。また取り外す日は正月七日あるいは十五日とする例が多い様です。
注連飾り
正月などに、家屋の入り口、門松、床の間や柱につける飾りのこと。
もとは一本の縄であったものが多様化し、装飾的になり、現在見られる様な形となりました。
注連飾りは、輪飾り、大根じめ、牛蒡しめなど、また注連縄につけるものとしては、裏白、橙、譲り葉が一般的ですが、地域によって様々です。
しめ縄は本来、内と外とを分け、災い、不浄なものの進入を防ぐ結界として神社などの聖域にはり巡らされるために用いられてきたものです。
【お供えと飾りの頁】
 鏡餅 鏡餅
 お飾り 目出度いいわれ お飾り 目出度いいわれ
 門松・注連飾り 門松・注連飾り
|