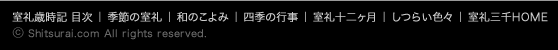|

|
|
嘉祥の儀の起源ついては諸説があります。その一つに、仁明天皇の848年、6月16日に16の数にちなんだ神供を供えて疫病が人体に入らないよう祈誓し、元号を嘉祥に改めたとする説があります。
室町時代には年中行事となり、江戸時代には朝廷や幕府のみならず町方でも嘉定喰(かじょうぐい)といって、十六文で餅16個を買い食す風がありました。徳川幕府では「嘉祥頂戴」と称して御目見得以上の諸士に大広間で七種(のちに八種)の菓子を賜る行事が催されました。
明治以降は廃れてしまいますが、1979年、全国和菓子協会によって6月16日は「和菓子の日」に定められました。
|
|
| |
| 「祝い七つ菓子」
おめでたい時に、身近にあるお菓子七種を盛ってお祝いすることをいいます。七の数は、東西南北に天と地、行事を実行する人の心を加えた数とされています。和菓子の日に「祝い七つ菓子」にちなんだ室礼をされてはいかがでしょう。
|

|
 |
|
| |

|
嘉祥饅頭と季節の野菜の盛り物
「和菓子の日」には、 和菓子屋の店頭に嘉祥饅頭が並びます。厄除けの五色の伝統的な饅頭です。

|
 |
|
| |
| 「水無月」と五色の嘉祥饅頭
「水無月」は鱗を模した三角の形と小豆の赤が厄よけの意を表します。(和菓子:とらや)
|

|
 |
|
| |
|

|